運動はあなたの健康寿命を延ばします
第19 回目のブログです。今回は運動と寿命に関するお話です。
WHOが公表した2023年版の世界保健統計によると、日本は世界一の長寿国であり、平均寿命は84.3歳とされています。男女別にみると、男性は81.5歳でスイスに次いで第2位、女性は86.9歳で第1位です。
日本人の長寿の要因については、さまざまな考察がありますが、一般的には人種・遺伝的要因よりも、生活・環境要因の影響が大きいと考えられています。人種・遺伝的に日本人に近いとされるアジア諸国の中では、韓国、シンガポールが世界第3位、第4位と長寿ですが、中国は世界第48位であり、その他のアジア諸国もそれ以下であることを考えると、人種・遺伝的要因はそう大きくないと思われます。
生活・環境要因による長寿の理由としては、①和食を中心とした食文化、②医療体制と国民皆保険制度、③公衆衛生と生活環境の整備など、複合的な要素が挙げられています。和食は野菜等の食物繊維に富み、発酵食材で調理され、脂肪摂取量、総カロリー摂取量が他国に比べて著しく少ないことが健康長寿に繋がっていると考えられています。また、医療体制や公衆衛生体制が国全体で整っており、国民の衛生意識も高い(コロナ禍におけるマスクの装着率の高さはその好例です)ことが、日本人の平均寿命の底上げに寄与していることは間違いありません。
長寿であることは好ましいことですが、寿命を全うする前に健康が損なわれている期間が長いとすればそれはあまり喜ばしい状況とは言えません。近年、日常生活に制限なく、健康な生活を送ることが出来る年齢を健康寿命と呼んで、それがどれくらいまで長く保たれているかが注目されています。
世界の健康寿命のランキングをWHOの統計で見てみると、日本は健康寿命でも第1位で74.1歳でした。第2位はシンガポール、第3位は大韓民国、第4位はスイスと、平均寿命が長い国が健康寿命も長い傾向にありました。こちらも日本は世界第1位で喜ばしいことですが、平均寿命との差をみると10年の開きがあり、健康が損なわれている期間は思いのほか長いことが分かります。
日本の都道府県別で健康寿命を比較したデータを見ると、健康寿命が最も長いのは静岡県でした。その理由としては、お茶の消費量が多いこと、高齢でも働く人が多いことが挙げられています。働くことは体を動かすことであり、運動量が多いことが考えられます。また、県政として健康寿命を延ばすことに取り組んでおり、健康長寿の三要素として、運動、食生活、社会参加を掲げ、県民への働きかけをしています。
健康寿命と身体活動に関しての疫学研究としては、2024年に中国における65歳以上の高齢者2,500人を対象とした観察研究の報告があり、身体活動量の多い人ほど日常生活に制限のない状態が維持されており、すなわち健康寿命が長くなることが期待されるデータが得られています1)。今年、2025年には、健康寿命を延ばすために運動が重要であることを提唱する総説論文が相次いで発表されています2)3)。これらの報告では、有酸素運動、レジスタンス運動(筋トレ)、バランス運動、柔軟運動といった多様な運動が健康寿命の延伸に効果的であるとされています。
健康寿命を延ばすことは皆さんの人生後半の生活をより豊かに実りの多いものにし、ご家族や社会の負担を軽くする事にも繋がります。地域、国レベルで考えれば、医療費の削減にも寄与することが期待されます。医療従事者、医療行政が運動を医療の大事な柱、すなわち“運動は薬”という視点を持って、運動を診療の中にもっと積極的に取り入れていくべきと私は考えています。
資料
1)BMJ Open. 2024; 14(2): e074573
2) J Nutr Health Aging. 2025; 29(1): 100401.
3) J Appl Physiol (1985). 2025 Apr 17.
“運動は薬”外来の詳しい内容はこちら
https://www.miyanomori.or.jp/undou/
<プロフィール>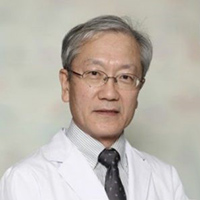
鐙谷 武雄(あぶみや たけお)
当院副院長、専門は脳神経外科で、中でも脳血管障害(基礎研究に長らく従事してました)
運動習慣は、出来るだけ毎日のストレッチと8㎏ダンベルでの筋トレ、週2回程度のランニング、不定期の10分間HIIT(高強度インターバルトレーニング)、たまのゴルフです
