運動は呼吸機能を高めて肺疾患予防しますが、ひどい咳・息切れが出たら要注意です
第24回目のブログです。今回は運動が呼吸器に与える影響について紹介したいと思います。
運動時には筋肉は酸素をより消費するため、肺は呼吸回数を増やし、換気量を増やします。継続的な運動は呼吸筋の強化、肺活量の増加、換気効率の改善をもたらし、肺疾患の予防や回復に役立つことが知られています。
運動と肺炎発症の関係を調べたメタアナリシス*研究では、10件の前向き研究、約100万人のデータをまとめた結果、運動をすることで肺炎の発症リスクが31%低下していました1)。この予防効果については、運動が免疫機能を高め、炎症反応を軽減させることが要因と考えられています。この研究は細菌性肺炎に関するものですが、2019年以降はウイルス性肺炎である新型コロナウイルス感染症での重篤な肺炎が世界的に流行したのは記憶に新しいところです。この新型コロナウイルス感染症についても12の研究、約126万人を対象としたメタアナリシス研究で、中~高強度の運動していることにより、入院率が42%、重症化率が35%、死亡率が53%と、いずれも有意に低下することが明らかとなっています2)。また、上気道炎、いわゆる一般的な風邪についても、約1000人を対象とした前向き観察研究で、運動により風邪に罹患している期間が46%短くなり、さらに症状の重症度も軽減されることが示されています3)。慢性の肺疾患についても運動効果を検討した研究があり、英国の約27万人を10年追跡した結果では、身体活動が中~高強度レベルの人では、慢性閉塞性肺疾患の発症リスクが23%低下していました4)。
一方、肺疾患の治療の一環としても運動は重要視されています。運動療法(呼吸リハビリテーション)は病状の改善に欠かせないものであり、慢性閉塞性肺疾患において標準治療のひとつです。運動療法は息切れの改善、運動耐容能の向上、生活の質(QOL)の改善に加え、再入院率や死亡率の低下に結びつきます。また、気管支喘息、間質性肺疾患、肺高血圧症においても、適度な運動療法は酸素効率の改善や炎症の抑制に寄与し、症状の改善につながることが知られています。
このように運動は基本的に肺の健康に有益ですが、注意が必要な場合もあります。きつめの運動をある程度の時間継続して行うと、その後に激しい咳が止まらなくなることがあります。これは運動誘発性喘息と呼ばれ、激しい運動で呼吸が速くなる際、特に乾燥した冷たい空気を吸い込むと気道が刺激されて一時的に気道が狭くなるために起こります。私自身も中学生の時に経験があるのですが、体育の時間に中距離走の記録測定をしたところ、次の時限の授業でクラス中の生徒がずっとせき込んでいたため、担任の教師が驚いて保健室に連絡していたことを思い出します。普段あまりきつめの運動をしていない人は、急な激しい運動で誘発されることがあるので注意が必要です。また、運動後に咳ではなく息切れが強く出る場合には、何らかの疾患が隠れている可能性があります。肺の疾患としては、前述の慢性閉塞性肺疾患、肺線維症、肺炎などの可能性があり、また循環器系の疾患であれば、心不全、狭心症などの可能性があります。また、貧血が高度になると酸素が十分に供給されないため息切れを生じることがあります。階段を上がったり、横断歩道を急いで渡った時など、さほどの運動でもないのに息切れが強く出るようであれば、一度病院を受診されることをお勧めします。
*メタアナリシス:複数の研究結果を統計学的に統合し、より信頼性の高い結論を導き出す手法
参考文献
1) GeroScience 2022; 44: 519–532.
2) Rev Med Virol. 2022; e2349.
3) Br J Sports Med. 2011; 45(12): 987-92.
4) BMC Med. 2022; 20(1):70.
“運動は薬”外来の詳しい内容はこちら
https://www.miyanomori.or.jp/undou/
<プロフィール>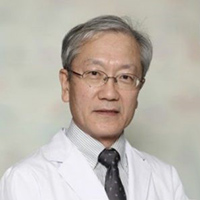
鐙谷 武雄(あぶみや たけお)
当院副院長、専門は脳神経外科で、中でも脳血管障害(基礎研究に長らく従事してました)
運動習慣は、出来るだけ毎日のストレッチと8㎏ダンベルでの筋トレ、週2回程度のランニング、不定期の10分間HIIT(高強度インターバルトレーニング)、たまのゴルフです

